発達検査の方法はたくさんありますが、時期というのがあります。
発達検査と知能検査があるのを、ご存知でしょうか?
発達検査はだいたい1種類。
知能検査は3種類に分かれます。
発達検査と知能検査の違い
この違いの1つは適用年齢があります。
発達検査を、1番始めに受けることがおおいと思いますが、発達検査は乳児も対象になります。
例えば3歳児検診などで「発達テストうけますか?」と言われた場合、だいたい発達検査になります。
知能検査は物事に関する理解、何かの課題の解決の仕方など、認知能力を中心に検査していきます。
反対に発達検査は身体の機能や、社会性を含めた幅広く検査ができます。
乳児にたいして知能検査は難しくなってくるので、発達検査を使用していきます。
次に、種類を書いていきます。
新版K式発達検査
これは代表的な発達検査の1つです。
他にも種類があるのですが、新版K式発達検査が出来てからは、この形式が使われるようになっています。
開発されたのが京都なので、京都では幼児以降も使われることが多いです。
もともとは0歳~10歳で、次に13歳まで拡大され、今の新版K式発達検査2001では成人まで適用されています。
子どもの発達の偏りを
- 「姿勢・運動(P-M)」
- 「認知・適応(C-A)」
- 「言語・社会(L-S)」
で検査結果があり「全領域」で発達年齢と発達指数が表記されます。
3歳以上の子どもには
- 「認知・適応(C-A)]
- 「言語・社会(L-S)」
に重点を置いているようです。
このとき検査をしてくれる心理士さんは言語の反応・感情・情緒・動作なども記録して総合的に判断していきます。
息子が受けたのは、この新版K式ですが詳しい心理判定結果報告書を後日郵送してもらうことができます。
そこに心理判定の所見などが記載されており、支援が必要な箇所などの記載があります。
そこに多弁であったり、コミュニケーション能力の凸凹などが書いてありました。
必ず郵送してくれる訳ではないので検査を受けて、心理判定結果報告書がほしい場合は、一言、心理士さんに声をかけるといいと思います。
我が家ではこの報告書を持って、進学の相談に校長先生とお話をしました。
田中ビネー式知能検査Ⅴ
こちらは知能検査になりますが、総合的な知的水準しかわからないため、認知機能の凸凹や不得意得意までは分かりにくい為、あまり使用されることはなくなってきました。
WISC
こちらはアメリカで主に使用されている形式ですが、日本向けに使えるように改正されたりするのが、数年という年単位での時間が必要なので最新版がアメリカとは違います。
内容も複雑で検査時間が長くなってしまうので、子どもが飽きてしまったり、出来ないことによりやる気をなくしてしまったりと、子どもに負担やストレスを与えてしまう場合もあります。
また、時間が長く内容も複雑なので、IQが低く出てしまうこともあります。
適用年齢は5歳~17歳未満。
内容がやや難しいので1番の問題は点数を取れない検査が、いくつかあると知能指数を算出できないのです。
なので、検査をするのであれば、小学校高学年や中学生ぐらいのほうが安定してくるでしょう。
小学生低学年では難しい問題も多いので、受けてみても、指数算出が出来ないということにもなりかねません。
算出できない(知能指数50以下の場合も)正確な数値が出てこないので、田中ビネーや新版K式で再度行ったりすることになります。
診断書や報告書を書いてもらうことも可能です。
WAIS-Ⅲ
こちらの対象年齢は17歳以上です。
感覚的にはWISCの成人版と言った感じです。
こちらもWISCと同様に、時間がかかりやすい検査となっています。
算出出来ない場合や知能指数50以下の場合の、テストの切り替えの必要性もWISCと同様です。

検査実施の時期に注意
例えば療育手帳の交付を考えていたり、児童福祉センターなどで発達テストを行う場合、ほぼ新版K式発達検査が適用されます。(これは地域の違いもありますので確認してみてください)
医療機関はWISCが多いようですし、センターでもこの形式を扱える心理士さんがいらっしゃれば検査を受けることが出来ます。
どちらにせよ発達障害というのは、1度検査を受けたからと言って全てがきまるわけではありません。
子どもの体調や気分、情緒によっても判定結果は左右されます。
なので、1度受けた後に観察をして経過をみていくことが、大切なことになっています。
また、今では知的障害を伴わない発達障がいがあるため、さらに経過観察が必要でしょう。
この経過観察の期間ですが
- 1歳~3歳未満は3か月以上
- 3歳以上は6ヶ月以上
- 7歳以降は1年~2年以上
の期間をもつことがいいと言われています。
頻繁に検査を行うと検査内容を覚えてしまったり、伸びしろがわかりにくいなどの問題が起こり、正確な指数がわからなくなってしまいます。
親としては発達の伸びは気になるので、頻繁に受けたいところではありますが「期間を開ける必要がある」のです。
節目に発達検査を受けられない!
小学校進学にあたり、普通級がいいのか支援級がいいのか悩みますよね。
その時の1つの指標が発達テストだったりするわけです。
上でかいた「期間が必要」というのがここで出てきます。
年中から年長にあがる春ごろに発達検査をうけたとしたら、進学のことで悩みだす夏ごろに、テストを受けられない可能性も出てくるのです。
実際、私の身内で受けられない人がいました。
年中から年長になるにあたりで心配で検査を受けたが、進学に悩みだす夏に、もう1回うけようとしたら受けられなかったので、期間が空いたギリギリにテストを受けたかたがいます。
そうすると親も不安になり、ばたばたしてしまい、進学を決めるために早く動き出す時間が短くなってしまい、焦ってしまいますよね。
そうならないために年中あたりから、発達検査の時期は考えておいたほうがいいですね。
私もこの話を知っていたので、発達検査の時期は考えて動いていました。
教育委員会、医療機関で発達検査をうけるメリット、デメリットをまとめていますので気になる方は読んでみてください。

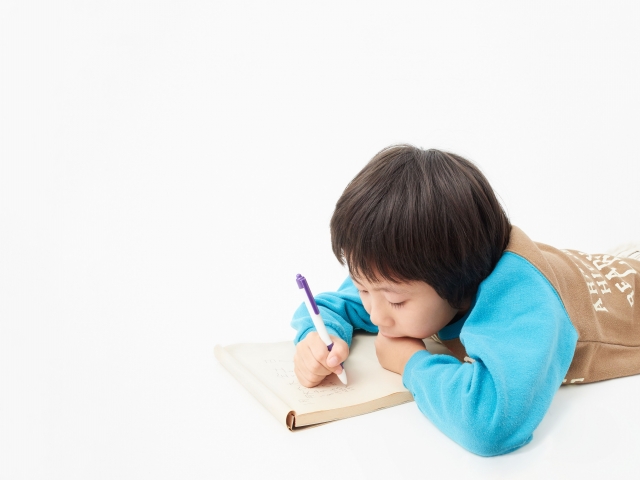

発達障がいの子どものためのタブレット教材はこちら
>>苦手な所はさかのぼり学習ができる無学年タブレット教材:すらら<<
お知らせと小話
このブログの内容が
発達障がいというナイーブな内容のため
コメントをしたいが出来ないという
お問い合わせを頂きました。
こちらのブログに関しては
コメントしても全体公開かどうかを
私が選べて基本的に公開しませんので
お気軽にコメントして頂ければと思っています。
コメントは公開しないと
私からの返信ができないので
ご了承お願い致します。
コメントを読ませて頂いて
お声が多いものを
記事にしたり、返信として
記事にさせて頂いたりするかもしれませんので
よろしくお願い致します。
人気ブログランキングに参加しています。
良かったらクリックおねがいします。
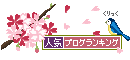
人気ブログランキング







