自閉症スペクトラム障がいは
年齢ごとに特徴ですが
子どもが成長していくとともに変化していきます。

変化のしかたは子どもそれぞれ
個人差が大きいので、この年代はこう!ということは
ないのですが大まかな特徴です。
0歳~6歳
発達障害とは生まれてすぐに
わかる障がいではありません。
その診断もそうですが、
幼少期から診察や経過をみて診断がつくことが多いです。
・周囲にあまり興味を持たない
→代表的なのが
「目を合わせない」
「他の子どもが何をしていても気にしない」
「名前を呼んでも反応がない」
「指差しをしない」
・周囲とコミュニケーションを取るのが苦手
→周囲に興味が無かったり、
コミュニケーションを取るのが苦手なため
1人遊びをしがちになります。
また一方的に話してしまったりします。
言葉の遅れやオウム返しなどが言語面での特徴です。
・強いこだわりがある
→周囲にあまり興味をもたないのですが
自分が興味のあることは
何度でも何度でも同じ質問をします。
また手順にもこだわりがある場合もあるので
「起きたら電気をつける」
「一番に水を飲む」など
自分の中の手順が変わってしまうと
混乱してしまって癇癪をおこしてしまったりします。
上記のような特徴ですが
ADHDにも当てはまるところがあります。
息子も「こだわり・コミュニケーション」には
当てはまっていました。
6歳~12歳
・お友達に混ざるのが苦手・難しい
→周りを見ずに、自分の好きな事を
自分の思い通りにしてしまう子が多い。
しかし基本的には1人遊びをし
何かしてほしいときに関わりを持ちにいってしまう。
相手の気持ちや察するということが苦手な子も多い。
息子も相手の気持ちを察するのが苦手です。
・柔軟な対応が苦手
→ルールを決めた遊びや、
ルール通りにすることが好きな子どもが多いです。
一方、その場その場でルールを変えられたり
柔軟な対応を求められるのが苦手。
・なんで?といった説明が苦手
→言葉を言葉の通りに受け止める子どもが多く
単語を覚えても意味まで理解するのが難しい場合がある。
自分の思っている事や
気持ちを言葉にするのが苦手で
想像したりするのも苦手なので
「なんでなの?」
「どうやったの?」
などといった説明がうまく出来ないことがある。
息子は別の意味で苦手です。
支援方法
1、簡単な言葉できちんと伝える
→曖昧な表現はさけて
簡単な理解しやすい言葉で
ゆっくりと話してあげましょう。
2、その場で注意する
→「昨日、○○したらダメだったよ」
などと今のこと以外を話に出されると
時間軸が繋がらず混乱してしまう場合が多いので
その場ですぐに注意するようにしてください。
3、予定の変更は避ける
→こだわりや柔軟な対応が苦手なため
予定の変更をしてしまうと
とても不安になってしまう子が多いです。
しかし、絶対に予定の変更をしないと言うのは無理なので
変更するときは分かった時点で子供に伝えるか
紙や絵に描いてその子に分かりやすいように
説明し丁寧に伝えてあげてください。
4.視覚を使ったコミュニケーション
→言葉以外でコミュニケーションを取る手段として
写真や絵カードなどもためして
子ども本人が理解しやすいようにしてあげてください。
息子が使っていた絵カードです。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16c1837f.c5b0a2bd.16c18380.b798c889/?me_id=1282386&item_id=10000101&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faddplus%2Fcabinet%2Fio%2Fst0621_000.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faddplus%2Fcabinet%2Fio%2Fst0621_000.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
スケジュールポケット3点セット&絵カード(1)(2)セット
|
いきなりセットで買うのは不安だったので
最初は1セットで購入した所
分かりやすかったようで、
理解をしてくれやすかったです。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16c1837f.c5b0a2bd.16c18380.b798c889/?me_id=1282386&item_id=10000026&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faddplus%2Fcabinet%2Fio%2F0094.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faddplus%2Fcabinet%2Fio%2F0094.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
アドプラス 絵カード
|
しかし、ここで注意があります。
「絵カードは命令に使ってはいけない」と言う事です。
見通しを想像して繋ぎにくい子どものために、
見通しを持ち安心するために使わないと
拒否感や拒絶感が出てくる場合もあります。
5、手順を具体的に1つ1つ教える
→人を見て人の真似をして
行動するのが苦手です。
折り紙でも「見て折ってね」は
とても苦手なのですね。
どんな風な手順で
どれぐらいの回数
どのように動かしていくか
などなど具体的に示して
目で見て(視覚)を使ってもらい
説明していきましょう。
息子もイラストや写真などで
1つ1つの作業を丁寧に伝えるのも効果的でした。
療育で別アプローチからフォロー
専門機関や病院や療育などで
使われている療育方法になります。
・ABA(応用行動分析)
→出来ない課題を細かく分けて(スモールステップ)
出来たらほめて(その行動を強化)
成功体験をかさねて自己肯定感を高めていく方法です。
この方法は他の障害や、教育
福祉、医療、スポーツの分野でも利用されています。
例えば、奥さんが旦那さんに洗い物を頼んだとします。
A(夫が洗い物をした)→B(妻がありがとうと伝える)→C(夫が次も手伝ってくれる)
など夫の意欲や自己肯定感が高まり
行動が定着しやすいのです。
逆に・・・
A(夫が洗い物をした)→B(妻が間違いなどを指摘する)→C(もうしたくない)
といったように不満が高まり
行動として定着しにくいのです。
子どもだけに使うと思う療育方法ですが
人間関係全般に使っていけるのです。
・PECS(ペックス)
→絵カードを使った支援プログラムです。
ABAの原理に基づいています。
・TEACCH(ティーチ)
→自閉症スペクトラムの本人と
その家族を支援する総合的なプログラムですが
日本では行っている所はまだ少ないです。
・SST(ソーシャルスキルトレーニング)
→ソーシャルとあるように
対人関係・人間関係を上手く行うために
社会生活技能を身に付けたり
自分の特性を自分でしっかり理解して
自己管理をするためのトレーニングです。
また家族を支援するプログラムもあります。
どの障がいもそうですが
本人もつらく受け入れがたい問題ですが
付き合っていく家族ももちろんのこと
悩んだり困ったりイライラしたりと
精神的に参ることが多いです。
しかし、精神的に参るほど
子どもと向き合い、
それだけ真剣に向き合っているのだと
私はそう思います。
関連記事
人気ブログランキングに参加しています。
良かったらクリックおねがいします。
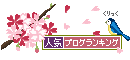
人気ブログランキング





